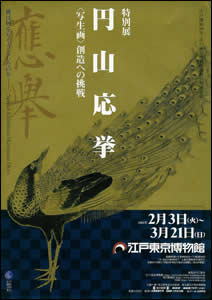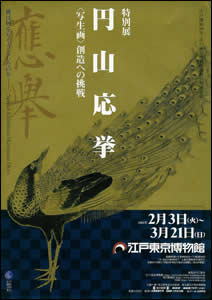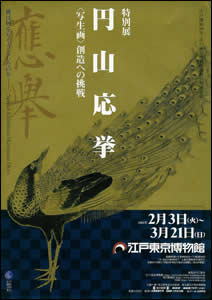
円山応挙 <写生画>創造への挑戦
昨日から東京会場展が始まった『円山応挙
<写生画>創造への挑戦』展
(江戸東京博物館)をさっそく見に行った。応挙展を見るのは没後200年を記念して開かれた展覧会以来10年ぶり。その当時は応挙の素晴らしさ(というより凄さ!)に気づいていなかったので、強く印象に残ったのは男女の裸体の(かなり)真迫な写生図くらいだった。しかしその後、東京国立博物館、松岡美術館、大倉集古館、三井文庫、千葉市美術館等のコレクションや日本美術の様々な企画展で応挙の作品をいろいろ見るにつけ、その筆力はもちろん写実精神や水墨山水画などの清新さ、そしてまた空間性を巧に生かした画面構成力などなどにほとほと感心し、自分の中では狩野探幽と双璧をなす存在の絵師になった。
そして今回の展覧会。制作年もモチーフも作風も異なる作品をばらばらに見てきた印象が、どれくらいまとめられるか期待して見に行った。展覧会場に入ってみると、本展監修者の応挙に対する明快なアプローチに基ずく展示になっていた。曰く、「実の写生」「気の写生」「虚の写生」「虚実一体空間」、という4部構成の展示。有名な《幽霊図》や龍虎図や故事逸話などを描いた作品は「虚の写生」の部類で、「虚実一体空間」には障壁画などで絵画空間と現実の部屋の空間を結びつけ一つの空間の如く演出した作品が含まれていた。確かにこうした明快な分類による展示は、多様な応挙の作品世界を理解するのにかなり役立つとは思う。もちろん展示解説などで個々の作品の魅力はきちんとおさえている訳だけれど、何かもう少し違うアプローチがあってもよいのでは、と思わないでもなかった。つづく。(2004年2月4日)
応挙展のつづきです。応挙の筆力は(筆法はオールラウンド!)それ自体で素晴らしいものだと思うけれど、それ以上に感心するのは技術的な卓越性が作品の質にマイナスに作用していないところ。例えば何点かある《牡丹孔雀図》でも、ある意味であれだけ装飾的で華麗な作品にもかかわらず、たんなる表面的、技巧的な作品にはなっていない。荒木寛畝だったかの《孔雀図》などと比べればそのへんは明らかだと思う(あれはあれで悪くはないが)。
ちなみに上手ということでいえば、早熟の天才狩野探幽には誰にも真似のできない優雅さがあった。障壁画でもいえるが《飛禽走獣図巻》などで清々しい輝きを放っている。下って幕末明治初頭の頃で上手いといえば河鍋暁斎が思い浮かぶが、暁斎の上手さは普通にいう・・・技術はあるけれど、などという批判の枠を遥かに超えたところがあって、上手さそのものが何かもう作品の批評的な力になっている特別なもののような気がする。
その点応挙の上手さは、作品になくてはならない技術でありながら表面に出過ぎることがなく実にバランスがよいと思う。しかし筆勢、筆触等に魅力がない訳では勿論ない。極端な例でいえば国宝『雪松図屏風』(東京展には出品されない)のあの松葉のさくさくとした描き振りは結構素晴らしいと思う。『雪松図屏風』といえば、あの松の樹形や画面構成もある意味で応挙の特徴をよく表している。つまり現実を作品という芸術に昇華しているのではない、ということ。それは光琳の《紅白梅図屏風》だと思う。しかし単に現実を写している訳でもない。それにしては余りにも見事なバランスだしリズムもあり簡潔かつ漠とした(あるいは幽玄な)空間性もある。つまりすぐれて美的なもの。しかし応挙の作のあるものからは現実感のリアリティ(変な表現?)がはっきり感じられる。応挙はここでも見事にバランスがいい。しかしこれは受身のバランスではない。ここまでくると創造の核のような気がしてくる。オーバーにいえば、芸術と人との関係のいくつかある究極の型の一つと言えるのではないか。現実と美的なものとの高度なバランスを保った作品が穏やかに目の前にあるが、応挙の作品の在りようは意外にも絵画とは何か?ということを静かに照射しているのではないか。というのはやっぱりオーバー?(2004年2月6日)
金曜の夜は例によっていくつかの美術館で夜間延長開館している。これを利用しない手はないし、しかも今週は応挙展
の作品が25点以上も展示替えされている。という訳でまた両国の江戸東京博物館に応挙を見に行きました。
再見する作品も今回初めて見る作品もどれも素晴らしかったですが、とくに今週から展示されている何点かの山水図には惚れ惚れ。伝統的な描法を用いつつも、お決まりのパターンを積み重ねて構成されているような山水図ではなかった。まあそういう作品もありますが、《雨中山水図》(二曲一隻、1769年)など、実に繊細な筆致で煙雨濛々とでもいった世界を、下手な文人画などより遥かに清々しく大きな世界として描いている。また《山水図》(4面、1794年)もほんとうに素晴らしい。横長の画面が4面続いていて、山野辺というか里山のありふれた、いかにもといった風景が描かれている(もちろん川が流れそれらしき橋も架かっている)。実景を描いたのではなく、山水画の一種のステレオタイプな訳ですが、その画面の展開する緩やかなリズムと静穏な気配はたまらない。しかもある意味で無駄がなくコンパクトでもある。しかし変に造形がかっていないところがまたよい。画面から感じられる気配は奥行きのある画面構成にも因っていると思うけれど、何よりも応挙その人の資質によるところが大きいと思う。応挙にもひそかに美の理想があったかも知れないが、少なくとも造形だけで終わってしまうような愚に陥らない結構な天稟を持ち合わせていた、のだろうと思う。(2004年2月20日)
目次
HOME